こんにちは。
不登校から生きる力を育むコーチ 柴野あさぎです。
HSC(繊細さん)は周りの空気を読み過ぎてしまうため、学校生活では不安を抱えがちです。
我が家のHSCよりの娘も環境が変わったところ、不安が増えたため、次第に学校を休むようになりました。
この記事では、自信を無くしてしまったHSCの娘へどのように対応したのか、体験談としてまとめました。
HSCにとって学校は疲れる場所なので、ストレスのケアや本人の自己理解が大切です。
ひたすら傾聴して、気持ちを受容するのがよかったので、ぜひ読んでみてくださいね。
HSC小学生の娘が学校に行きたくない3つの理由
娘は以前1年とちょっと不登校からの五月雨登校(別室)を続けていました。
そして、復学支援のサポートを受けて、教室登校がやっとできた!という経緯があります。
- 家族のルール見直し
- 過干渉をやめる・子どもを褒める
この二つを実践することで、親子関係が改善され、外に挑戦しやすい体制が整いました。
でも、HSCの場合は学校自体が疲れる場所だから、自己理解と不安な感情へのケアがプラスで必要だったのです。
一旦は学校に通えていたのですが、またしばらくすると「学校に行きたくない」と言うようになりました。
学校に行きたくない理由は3つありました。
相手の気持ちを読み過ぎて疲れてしまう
- 新しい先生がちょっと怖い
- 友達とのトラブルで疲れてしまった
娘は先生が他の生徒を叱った時に、かなり恐怖を感じていました。
先生が叱った次の日は、「まだ先生が怒っていたらどうしよう?」と不安そうでした。
 あさぎ
あさぎ相手のことを気にしたって、どうしようもないのですが、HSCなので考えてしまうのですよね。
朝起きられなくなった
学校に行きたくない気持ちや、授業への不安があり、娘はなかなか寝付けません。
就寝時間が23時半になり、朝起きるのは9時~9時半。
休み始めのうちは、朝が遅いだけで「もう無理~」と学校を諦めていました。
行きたい気持ちはあるのに、通学団に間に合わないので悔しかったみたいです。
イベントへの不安
久しぶりのプールや一泊二日の野外活動、高学年のプレッシャー…。
HSCにはハードルの高いイベントが続いています。
特に初めてのことには、些細なことも心配になり不安を抱いていました。



HSCが不登校を乗り越えるには?【HSCの理解と自己受容がカギ!】
学校のイベントや先生に不安を感じて、「学校に行きたくない!」「もう無理」を連発する娘。
精神的にも不安定なので、ひとまず学校をお休みすることにしました。
そして休んでからの娘の気持ちの変化や、私の対応をまとめました。
繊細さんは不安が多く、自信が無くなりがち
学校を休んだ当初の娘は、自分への自信がありませんでした。
自己否定感が強く、「どうせ無理だよ」って、学校や自分に対しても諦めている様子です。
- 多い宿題
- 先生への不安
- プールへの不安
- キャンプの準備や役割へのプレッシャー
- 朝が起きられない
いろいろ重なっていたので、自信がなくなるのも無理ないなぁ…。
みんなに合わせなきゃ、という想いもあったのでしょうね。



まずは、自分に自信を持ってもらうために、娘のそのままの気持ちを大切にするところから始めました。
話をしっかり聴く【傾聴する】
娘が感じた気持ちを大切にするには、私がしっかり話を聴く必要がありました。
なぜなら、子どもは自分の気持ち(感情)の扱い方を知らないためです。
「先生が怖かった!」という感情を、受け入れられないと、感情を我慢することになってしまいます。
だから、私が「そうなんだ。それは怖かったね~。」と聴いて返してあげるのです。
例えばこんな感じです。
娘「先生が授業で怒っていて、とても怖かったんだよ」
私「そうなんだ。急に怒られると怖いよね。」
娘「めちゃめちゃ怖かったんだよ。〇〇でね。〇〇なんだ…!」
私「うんうん。そんなことがあったら、びっくりするよね。」
私が相手の感じた感情で返すことで、娘がその後も話を続けるようになりました。
以前は「先生もいろいろ忙しくて大変なんだよ!」と、私の意見で返していたため、娘がしょんぼりしていたんです。
娘は怖い感情を話し切ると、満足したようでスッキリ感もありました。
この後、「先生だって神じゃないから怒ることもあるんだよ」「完璧な人間はいないもんね。」
とまた話し合いをしました。
子どもは視野が狭いので、物事を一方的に決めつけてしまうことがあります。
傾聴して、子どもが落ち着いてから、違う見解や考え方なども話し合いたいところです。
そして、こっそり学校に行き、先生が怒っていないのを確認すると、「先生怒っていない!教室に行けそう!」という思考に変わりました。
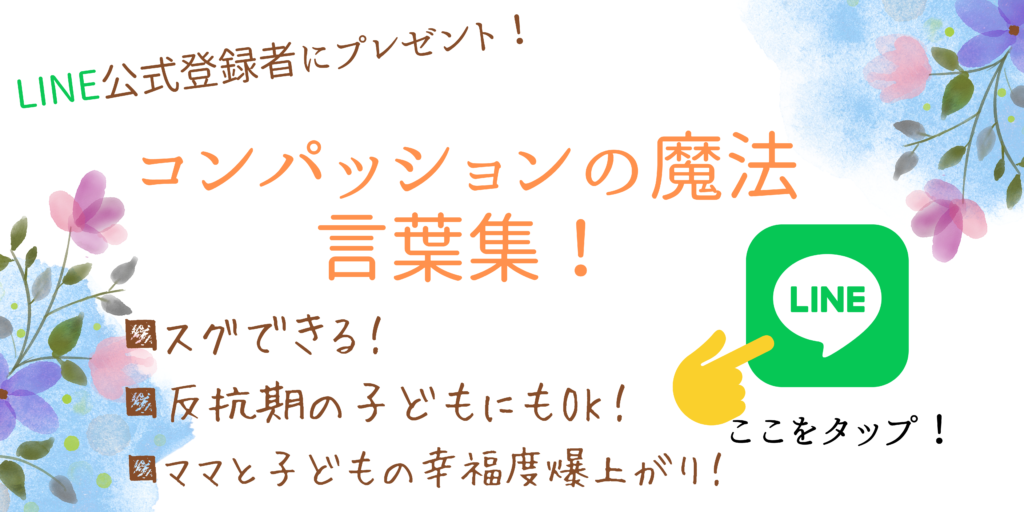
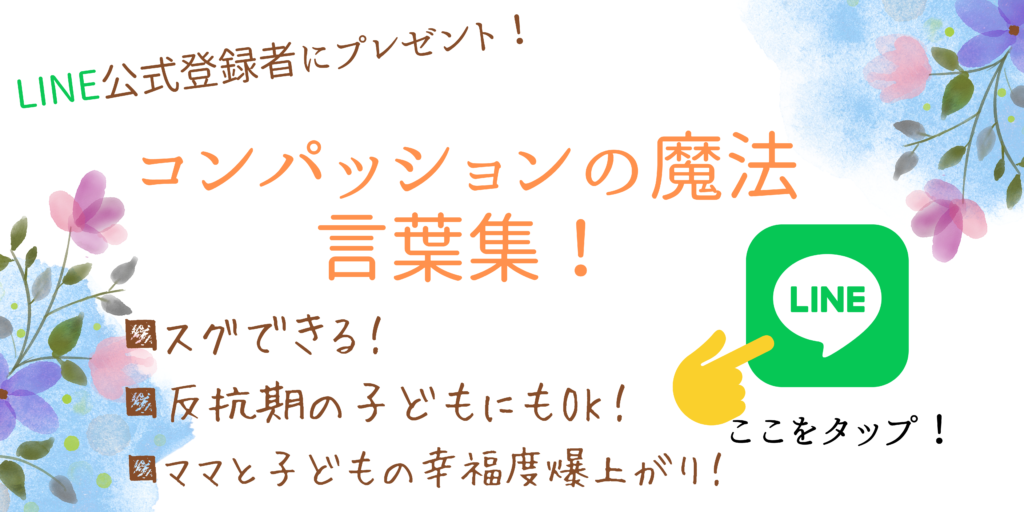
傾聴してもらうと感情が落ち着く【自己受容】
悔しさや悲しさ、恐怖を誰かに受け入れてもらえると、その感情が一旦落ち着きます。
誰かに分かってもらえると、「ありのままの自分でいい」と自分を肯定することができます。
「ありのままの自分でいい」と思える状態を【自己受容】と呼びます。
メモ
自分自身で感情を受け入れ、自己受容できるのが望ましいですが、子どもには難しいです。
大人の場合も、子どもの頃のトラウマや感情を我慢していると、自己受容が難しくなります。
娘の愚痴や不安を傾聴してからしばらくすると、「〇〇をやるー!」とか、「明日は〇〇ー!」
など自分からの前向きな発言が増えてきました。
HSCの理解を深めていった
娘は繊細ゆえに、余計なところに気を使っているため、傷ついたり疲れたりするのだと分かりました。
そこで本を参考にして、HSCさんの学校で過ごすための工夫を娘に伝授しました。
HSCの娘に「他人との境界線の引き方」の授業した~!
◆先生が怒っているのは先生の問題!オロオロする必要はありません。
◆先生に好かれようとしなくていい。
◆「先生おこってんな~。」それ以上考える必要なし。
◆先生より自分の気持ちに集中しよう。不安になったら深呼吸しよう!— あさぎ (@aoi2415) June 6, 2022
娘は以前にも空気読んで、自分の意見を我慢してしまうことが度々ありました。
でも、「言わないと誰も分からないし、自分を守るのは自分しかいないよ。」と伝えます。



こんな事も伝えました。
繊細さんのチェックや、楽に生きられる思考を伝えるのに役立ったのがこちらの本です。
自分を好きになる方法も書いてあり、実践的でとてもおすすめです!!



3行日記に今日あったいいことを書く【自己肯定感をあげる】
自分を認める、自信を持ってもらう一環として、夜寝る前に3行日記をつけるようにしました。
今日あったいい事を3つ書くだけの簡単な作業です。
娘は不安なことやネガティブなことを探すのが得意だけど、いいところを探すのが苦手でした。
でも気付くのが得意なら、意識するだけでポジティブな出来事も探すことができるはず!



書いたり書かない日もありますが、ゆるりと継続しています。
マイペースで教室に通う
まずは、途中から学校に通ってもOKなんだよ!というスタンスを伝えました。
不安を感じていると、夜眠るのが遅くなり、朝が起きられないという悪循環。
「私は起きられないからダメなんだ~…」
娘は周りと比較してしまい、自己肯定感を下げていました。
まずは、朝起きられない自分を受け入れてもらうことから始めます。
私は、起きたいのに起きられない葛藤に苦しむ感情を、傾聴して受け入れました。
- 「朝起きられないと悔しいよね。」
- 「昨日やるだけのことはやったよね。自分を責めなくていいんだよ。」
- 自分を責め出したら→「お母さんは今起きたあなたで大丈夫だよ。大好きだよ。」
こんなやりとりをしながら、本人の気持ちが落ち着くのを待ち、途中から学校に通える日もありました。
私は娘の意思を尊重して、送迎したり、相談に行ったり、困っている時は〇〇な方法もあるよ、などサポートをしていきました。



【まとめ】ありのまま自分でもOKと思えると、心が安定する
HSC(敏感な子)は、不安な感情を抱えやすいので、非HSCの子以上に「傾聴」が大切です。
また、自分の敏感な心のしくみを理解することが、
「このままの自分でいい」と思える第一歩になります。
もし本人が「怖い…」「無理…」と感じているなら、無理に押し出すのではなく、
柔軟な方法を一緒に探すことがおすすめです。
さらに、HSCの子は、親の感情や言動を敏感に察知しやすく、
✅ 親の期待に応えようとする
✅ 自分の気持ちを飲み込んでしまう
✅ 本音を言えずに心を閉ざす
といったことが起こりやすいです。
だからこそ、親自身が「不安・心配・イライラ」を受け入れ、安心感を持って接することがとても重要になります。
親が安心していると、子どもの不安も安心に変わる。
そんな関わり方を一緒に目指していきましょう。
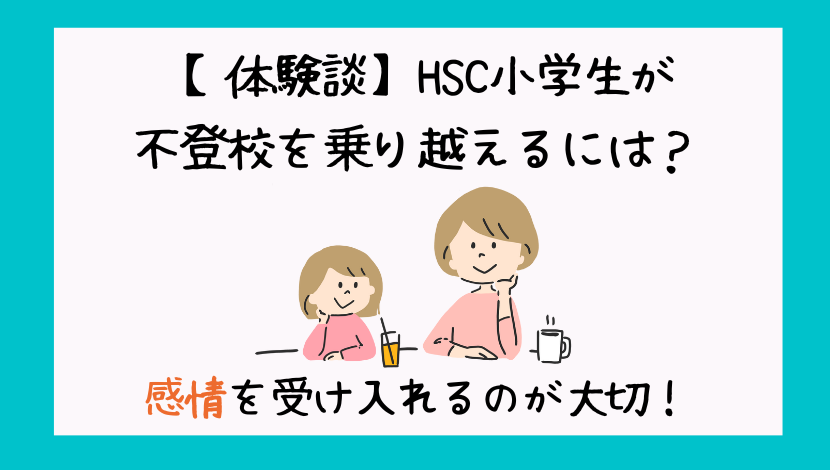


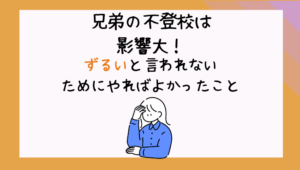
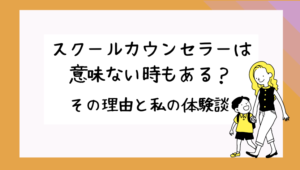
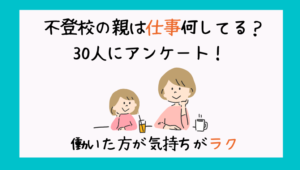
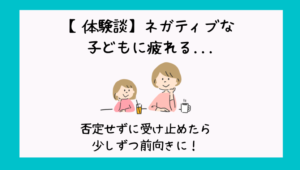
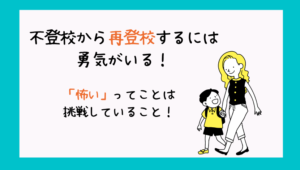
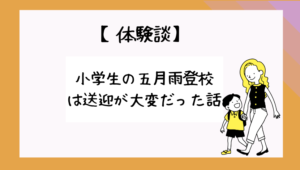
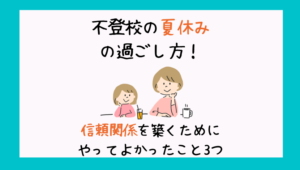
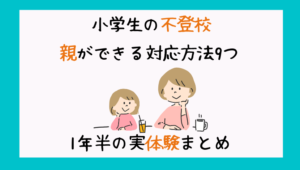
コメント